PR

このページはプロモーションを含みます
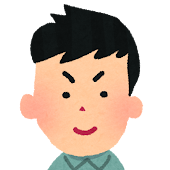
資格試験に本気で受かりたい

人生を変えたい
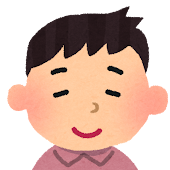
一度ダメだったけど、学びを変えて再チャレンジしたい

どんな講座が私に合うんだろう

どうしてもやり遂げたい
学校選びで迷わない!最短ルートで合格を目指そう
法律系資格や公務員試験は、人生のターニングポイントとなる大きな挑戦です。弁護士・司法書士・行政書士などの国家資格、公務員試験はどれもハードルが高く、独学での合格は難しいと感じる方も少なくありません。近年では試験制度の変更や出題傾向の複雑化が進み、正確な情報と効率的な学習戦略が合格のカギを握ります。
そこで注目されているのが、法律資格・公務員試験に特化した専門スクールの活用です。こうしたスクールでは、合格に直結するカリキュラムや教材、最新の試験情報を提供しており、効率的な学習が可能です。また、講師の丁寧な解説や個別指導、模試の実施など、学習継続を支えるサポート体制も充実しています。
とはいえ、法律資格や公務員試験対策スクールは全国に多数あり、それぞれ提供しているサービスや強みは異なります。授業スタイルも「通学型」「通信講座」「オンラインライブ」など選択肢が豊富で、自分に合った環境を見極めることが重要です。加えて、受講料も数十万円にのぼることが多いため、慎重な比較検討が必要となります。
本記事では、法律資格・公務員試験に挑戦する方に向けて、評判・合格実績・サポート内容・学習スタイルの柔軟性などを踏まえて厳選した「おすすめスクールランキング8選」をご紹介します。それぞれのスクールの特徴や魅力、選び方のポイントも丁寧に解説していますので、学校選びの参考にしていただければ幸いです。
自分に合った最適な学習環境こそ、合格への最短ルートです。この記事を通して、理想のキャリアに近づく第一歩を踏み出しましょう!
アガルートアカデミー
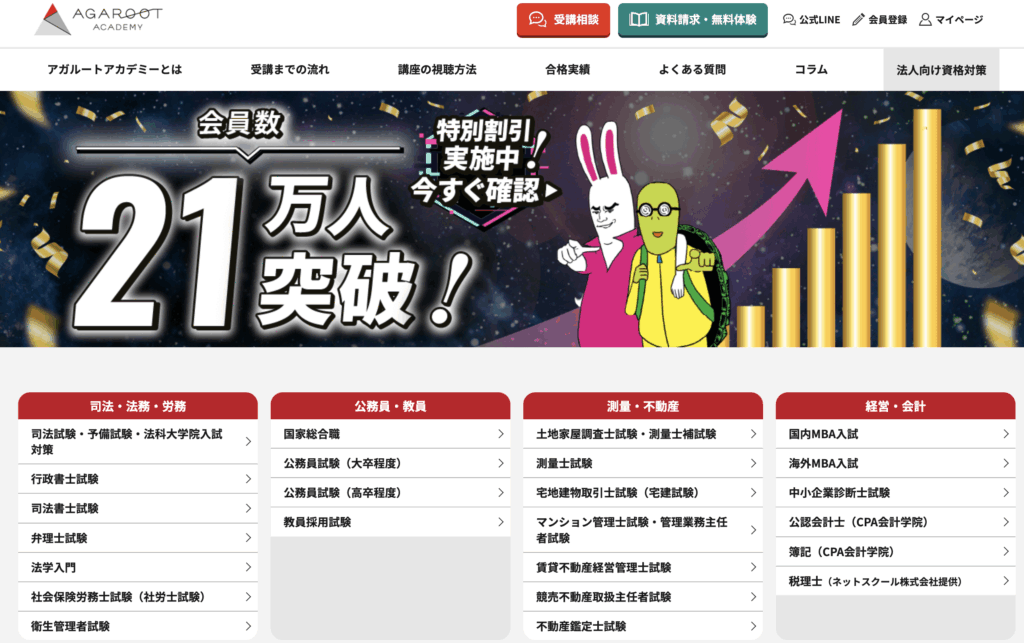
アガルートアカデミーについて
アガルートアカデミーは、2015年1月に開校した、オンラインによる講義の配信を中心とした資格予備校です。
社名である「アガルート(AGAROOT)」には、「受験生のキャリア、実力、モチベーションが上がる道(ルート)になり、出発点・原点(ROOT)になる」というポジティブな想いが込められています。
アガルートアカデミーは、「受講生が本当に必要としていること」を見極め、それをご提供することによって、受験生の道しるべとなるべく開校いたしました。
アガルートアカデミーは,司法試験等
法律系の難関国家資格を得意とする通信講座です。
講義は全て収録されたオンライン映像にて受講するため,
通学型の予備校よりも安く講座をご提供しております。
◆アガルートアカデミーが選ばれる理由◆
1.多機能な受講システム
オンライン講座なので場所,時間問わず,無駄なく受講できます。
また学習を手助けする機能が沢山あります。
・倍速再生(8段階速度調整,かつ最大3倍速)
・音声ファイルのダウンロード可能(ネット環境を気にせず学習可能)
・マルチデバイス(パソコン/スマートフォン/タブレット)対応
2.講師作成のオリジナルテキスト
申込後お手元にテキストが届き,スムーズに学習を開始できます。
基幹講座はフルカラーで,分かりやすいレイアウトなど工夫が随所に見られます。
内容は講師自ら出題傾向を分析し合格に必要な情報を詰め込みました。
3.通信講座ならではの充実したフォロー
Facebookグループによる質問対応,定期カウンセリング,直接指導など,
通信講座でも受験生をしっかりフォローします。
資格の大原

さまざまな受講スタイルが魅力。最新の合格ノウハウを学べる
公務員試験講座の受講方法・回数・料金・対象コースなどが細かく用意されています。どの講座でも、毎年の本試験傾向などを分析した実績豊富な講師陣による、短期合格に必要な指導を受講可能。不安や環境からくるストレスへのサポート制度や、集中しやすい自習室などの学習環境も整っています。
東京アカデミー

高卒・大卒者それぞれの公務員試験対策講座を開講
高卒・大卒者それぞれ向けの公務員試験対策講座が開かれています。全日制・夜間部・日曜部・短期講習など、通学できる時間帯に合わせて通学コースを開講するほか、オンラインコースや通信講座も用意。専門スタッフが常駐しており、日々の試験対策や個別面談のなかで、受講生に寄り添ったサポートをしているのが特徴です。
4位、LEC東京リーガルマインド

受講生を個別にサポートする担任講師制度が魅力
公務員試験指導30年以上のノウハウが凝縮された、合格カリキュラムを受けられるスクールです。受講生を個別にサポートする担任講師制度が特徴で、学習スケジュールや科目質問など目的に合わせて活用可能。通学・通信・オンラインなどの学習スタイルに対応し、3回分の講義を無料で試せるおためしWeb受講制度もあります。
グローバルアイ

アットホームな雰囲気と手厚いサポートが魅力
2024年度の最終合格率は85.1%を誇る公務員予備校です。一般的な学校のように担任制を採用しており、対面・LINE相談や、週1回の学習アドバイスなどが行われています。担任ホームルームやボランティア体験など、受講仲間と知り合えるイベントも定期的に開催されており、アットホームな雰囲気が魅力です。
資格の学校TAC

合格までの流れを導くオールインワンプログラム
筆記試験から人物試験対策までオールインワンの合格カリキュラムが特徴。各科目の講義はもちろん、担任講師の個別指導により、進路相談や面接相談など自分に合った方法で勉強を進められます。毎年本試験問題と受講生アンケートに基づいて、講義・教材が見直されているので、最新の試験傾向に合わせた講義を受けられますよ。
資格スクール 大栄

二次試験対策に力を入れたカリキュラムが特徴
公務員試験の難所である二次試験対策に特に力を入れており、志望動機・論文・面接などを専門講師がしっかりサポート。一次試験対策は学習効率・学習継続にこだわり、必要事項を凝縮したテキストや、直近の出題傾向から答案練習を用意しています。どの公務員コースか迷っている人向けには、無料ガイダンスもありますよ。
伊藤塾
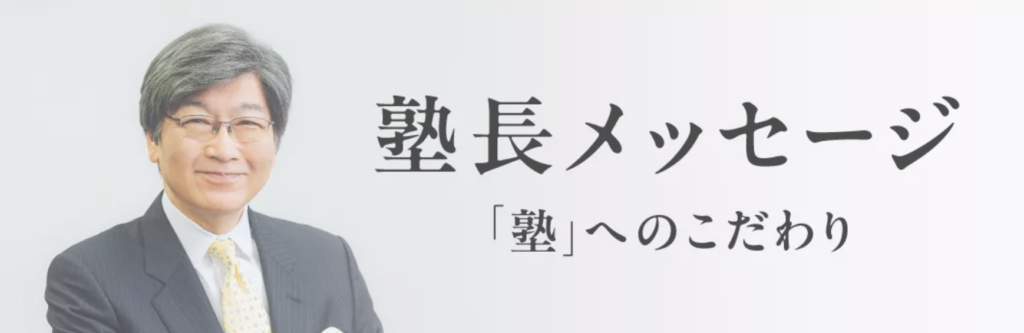
“合格のその先”を見据えた発想
伊藤塾は1995年の開塾以来、多数の法律家・行政官を輩出してきました。ただし、 ただ国家資格を有するのではなく、誰もがあらゆる意味において健やかに暮らし、幸せを感じられる世の中に寄与できる人材を送り出すこと。重要な目的はここにあり、試験合格はそのための必要最低条件である、というのが伊藤塾の一貫したスタンスです。合格から逆算した最も効率的な学習カリキュラムを提供しているのも、この考えに基づいています。 こうした考えは「合格後を考える」「ゴールからの発想」「盤石な基礎」といったキーワードとして、塾生・スタッフすべての意識に根づいています。
学びたい人に応えられる公平性
伊藤塾は、法律を学びたいと考えるすべての人にとって、いつでもどこでも頼れる存在でありたいと考えています。居住地域や周辺環境、年齢や職業に、学びの意志を妨げられるべきではないのです。業界内でいち早くインターネットによる講義・情報配信の整備を行ない、地域格差の解消に努めてきたのも、公平を期すための方策のひとつです。 伊藤塾は、塾生が最短距離で合格水準に達することにこだわり、かつ公平性・双方向性向上のため、講義提供における一方通行で限定的な枠を取り払うべく取り組みを続けています。
📅 計画策定:合格へのロードマップを描く
1. 目標設定と試験分析
まずは、受験する士業試験の合格基準、出題傾向、科目別の配点を徹底的に分析します。特に、過去数年間の出題テーマの変遷を確認し、**「何を重点的に学ぶべきか」**を明確にしましょう。
- 長期目標: 試験日から逆算し、**「いつまでに全科目のインプットを終えるか」「いつから本格的な過去問演習に入るか」**といった年単位、月単位のスケジュールを設定します。
- 短期目標: 毎日、毎週の学習量を具体的に決めます。「今週は民法の物権分野を完璧にする」「今日は過去問を30問解く」など、達成度を測れる目標にすることが重要です。
2. 学習時間の確保と習慣化
士業試験の多くは、合格までに数百時間から数千時間の勉強が必要とされます。合格者は例外なく、学習時間を生活の中心に組み込んでいます。
- ルーティン化: 毎日決まった時間に勉強する習慣をつけます。早朝、帰宅後の夜など、自分の集中力が最も高い時間帯を「ゴールデンタイム」として活用しましょう。
- スキマ時間の活用: 通勤時間や昼休みなど、細切れの時間には、暗記科目や一問一答形式のアプリを利用するなど、インプットの効率を上げます。
🧠 効果的な学習法:インプットとアウトプットの循環
1. インプット学習の鉄則:基本の徹底理解
専門的な知識は、ただ暗記するだけでは応用が利きません。「なぜそうなるのか」という趣旨や概念を理解することが、応用力を高める土台となります。
- テキストの精読: 初学者は、いきなり分厚い専門書ではなく、予備校の基本テキストや図解の多い入門書から始め、全体像を把握します。
- 講義の活用: 予備校の講義やオンライン講座を利用する場合は、**「聴く→復習する→問題を解く」**をセットで行います。ただ聞き流すだけでなく、重要論点を自分なりにまとめてアウトプットにつなげましょう。
- 重要論点のマーキング: テキストや判例集には、過去問で頻出している箇所や理解に時間がかかった箇所を色分けしてマーキングし、直前期の復習効率を高めます。
2. アウトプット学習の極意:過去問中心主義
士業試験対策において、過去問演習は学習の生命線です。過去問は単なる力試しではなく、**「出題者の意図」や「知識の使われ方」**を知るための教材です。
- 早期着手: インプットが一通り終わるのを待たずに、学習中の単元に対応する過去問に早い段階から取り組み始めます。
- 周回と分析: 過去問は最低3回は繰り返します。単に正解・不正解を確認するだけでなく、**「なぜ間違えたのか(知識不足か、問題文の読み間違いか)」**を分析し、間違えた理由を過去問集やテキストにメモします。
- 応用力養成: 過去問で問われた論点を深掘りし、「もしこの部分が変わったら答えはどうなるか」と考え、応用力を磨きます。特に記述式や論文式試験がある場合は、構成案の作成や時間を測っての答案作成を繰り返し行いましょう。
🚀 試験本番対策:万全の状態で臨む
1. 直前対策:総復習と弱点克服
試験直前期は、新しい教材に手を出すことを避け、これまで使ってきた教材の総復習に徹します。
- 重要論点の確認: 過去問で頻出しているAランク、Bランクの論点と、自分が苦手としている弱点箇所を集中的に復習します。マーキングしたテキストがここで役立ちます。
- 法改正への対応: 試験実施年度の法改正情報は必ず確認します。士業試験では法改正点が頻繁に出題されるため、改正内容を理解し、テキストに追加するなどして対応しましょう。
2. 模擬試験の活用
模擬試験は、本番の緊張感と時間配分を体験する貴重な機会です。
- 本番と同じ環境: 本番と同じ時間帯に、時間配分を厳守して解くことで、試験慣れします。
- シミュレーション: 難しい問題に時間をかけすぎないか、途中で集中力が途切れないかなど、自分の癖や弱点を把握し、本番での戦略を練り直します。
3. 当日の心構え:冷静さと時間管理
試験当日は、冷静さと正確な時間管理が最も重要です。
- パニック回避: 知らない問題が出てもパニックにならず、**「皆も難しい」**と割り切って、確実に取れる問題から解答します。
- 見直しの時間: 必ず数分間はマークミスがないか、問題文の指示(正しいものを選べ/誤っているものを選べ)を見間違えていないかを確認する時間を取りましょう。
士業試験は、**「正しい努力の量」**が問われる試験です。計画を立て、インプットとアウトプットを効率的に循環させ、最後まで諦めずに努力を続ければ、必ず合格は近づきます。
公務員予備校の費用相場は?
公務員予備校の費用は、学校や選ぶコースによって差がありますが、年間でおおむね20万〜60万円程度が一般的です。ただし、全日制の専門学校を選ぶと、さらに高額になることがあります。独学で参考書や問題集を購入して勉強する場合と比べると、やはりまとまった費用がかかるといえるでしょう。
一方、通信講座は通学するスタイルに比べて比較的費用が抑えられる傾向があります。費用をなるべく抑えたい人には通信講座の検討がおすすめです。
公務員予備校の通学期間と1日の勉強時間は?
公務員予備校には、はっきりと決まった通学期間がないケースも多いです。入学の時期が自由な学校も多いため、勉強を始めるタイミングは、目指す試験の難易度や1日に確保できる勉強時間を考慮して決めましょう。志望する試験の種類によって、必要な学習時間も変わります。
たとえば、国家公務員や地方上級公務員を目指す場合、800~1,200時間程度の勉強が必要とされています。一方、地方公務員の中級や初級レベルなら、おおよそ500~800時間が目安です。もし国家公務員試験を目指す場合、毎日3時間の学習時間を取ると、準備期間は約270~400日程度を見積もる必要があります。
社会人など勉強時間を取りづらい人は、試験の1年から1年半前を目安に予備校へ通うのがおすすめです。筆記対策を効率良く進めることで、面接対策や情報収集も並行しやすくなります。勉強時間は人それぞれ違うため、自分に合ったペースで余裕を持って進めることが大切です。
公務員予備校を選ぶポイント
公務員予備校を探す際は、以下の4つのポイントをチェックしましょう。
1. 学年や志望職種に対応した予備校を選ぶ
予備校によって、対応する学年や職種が異なります。自分が通える学年かつ、受験を希望する職種に対応したコースが用意されているかを確認することが重要です。多くの予備校は高校生から社会人まで幅広く対応していますが、一部で高校生を対象にしていない場合もあるので注意が必要です。
また、1科目だけの集中講座やSPI、人物試験に特化した講座を持つ予備校もあります。独学をベースにしながら、苦手な分野や二次試験の対策を予備校で補うという方法で、費用を抑えることも可能です。目標に合わせて無駄なく学べるコースを選ぶことがポイントです。
さらに、公務員試験には年齢制限がある試験も多いため、自分の年齢で受験資格があるかも必ず確認しましょう。国家公務員試験では、30歳が受験可能な年齢の上限となっているケースが多いです。なお、受験時ではなく就職時の年齢が基準となる場合もあるので注意してください。
2. 二次試験対策が充実している予備校を選ぶ
面接や小論文などの二次試験は個人で対策するのが難しい分野です。そのため、二次試験対策が充実している予備校を選ぶと安心です。特に社会人経験者枠で受験する場合は、面接指導の質が合否に大きく影響するため、チェックしておきましょう。志望先に合わせた具体的なアドバイスをもらえる予備校なら、効率よく準備が進められます。
近年は、面接試験を重視する自治体が増えています。面接試験には個別、集団、集団討論など様々な形式があり、グループワークやプレゼン、録画面接やWEB面接が導入されることも多くなっています。短時間で自分をしっかりアピールする力が問われるため、試験形式に応じた対策をすることが大切です。
予備校ごとに二次試験対策の内容や料金、模擬面接の回数などは異なります。例えばLECでは、受講生は何度でも無料で模擬面接を受けられる制度があります。個別面接だけでなく、集団面接やエントリーシートの添削が可能かも確認しておきましょう。
3. 模擬試験に対応している予備校を選ぶ
模擬試験を実施している公務員予備校を利用すると、本番さながらの緊張感や雰囲気を体験でき、試験に向けた心構えが整いやすくなります。模擬試験では、実際の試験に近い出題傾向の問題に挑戦できるため、自分の弱点を把握したり本番のペース配分をつかむ練習になります。
模擬試験のメリットは、試験本番前に出題の可能性が高い問題に触れられることです。苦手分野を知り、早めに対策することで合格への道が開けます。また、本番で初めて見る問題に慌てず対応できるのも利点です。
4. 通信講座を活用してスキマ時間を有効に使う
社会人など、まとまった学習時間が取りにくい方には通信講座も良い選択肢です。通信講座なら、通勤やちょっとした空き時間に、自分のペースで学習を進められます。ライフスタイルに合わせて通学か通信か、無理なく続けられる方を選びましょう。
通信講座は、自宅など好きな場所で時間に縛られず学べるのが魅力です。さらに、通学講座よりも費用が抑えられる点も大きなメリットです。近隣に公務員予備校がない方や、通学が難しい方、費用を抑えたい方には特に向いています。
ただし、通信講座は質問がしづらいことや、すぐに問題解決ができないデメリットがあります。また、自己管理が必要になるため、計画的に勉強を続けられる人に適しています。
【まとめ】法律資格・公務員試験スクール選びは未来への投資
法律資格や公務員試験は、合格すればその後のキャリアや人生に大きな可能性を開く一方で、試験の難易度は非常に高く、独学では限界を感じることも多い分野です。だからこそ、多くの合格者が活用しているのが、法律資格や公務員試験に特化したスクールの存在です。
今回ご紹介した「法律資格・公務員試験スクールランキング7選」は、合格実績やカリキュラムの質、講師の指導力、サポート体制、そして学習スタイルの多様さなど、あらゆる面で信頼できるスクールばかりです。どのスクールも強みや特色が異なるため、自分のライフスタイルや学習方法、目指す資格に合わせて選ぶことが何より重要です。
法律資格や公務員試験の勉強は、時間もお金もかかる大きな挑戦ですが、未来の自分への投資だと考えれば決して無駄にはなりません。この記事を参考に、自分にぴったりのスクールを見つけ、合格への一歩を踏み出してください。あなたの努力が必ず実を結ぶことを願っています。